カミュ VS サルトル論争の再検証のために
<お知らせ>
ツイッター上で、「カミュVSサルトル論争」を題材に、自由な討論を行います。
◆テキスト カミュ/サルトル/ジャンソン共著『革命か反抗か』(新潮文庫)
◆サブテキスト 今回のはてなダイアリー(カミュ・サルトル論争の再検証のために)、なおアメブロでも、今回のはてなダイアリーと同文を掲載しています。
◆参加資格 自由な討論ですので、参加資格を問いません。「カミュVSサルトル論争」へのアプローチも、文学的、思想的、政治的、どんな方法でも構いません。左翼も、右翼も、キリスト者も、イスラムの方も、仏教徒、神道の人も、唯物論の人も、唯心論の方も、どなたでも結構です。学術的なシンポジウムではありませんので、ラフに語っていただいて構いません。
◆参加方法 ツイッターで、ハッシュタグ #夢のあとサロン をつけてつぶやいてください。
実施期間は、2013.6.29〜7.6です。
私のIDは、@harapion です。
#夢のあとサロン をつけてつぶやいていることに気付いたら、https://twitter.com/harapion/le-salon-après-un-rêve に追加し、眼で追えるようにします。
私が気づいていない様子でしたら、@harapion までお知らせください。
なお、#夢のあとサロン をつけての「カミュVSサルトル論争」に関するつぶやきは、後で「NAVER まとめ」に引用する可能性があります。
その場合でも、使用しないでくださいという意向でしたら、まとめには加えませんので、ご安心ください。
◆今後の予定 今回、もしも好評であれば、こうした現代の古典や、現在進行形の文化を題材に、シリーズ化していく可能性があります。今後の展開にご期待ください。
1.前史
◆「不条理と反抗の作家」である。
ジャーナリスティックには実存主義系作家に分類して良いが、厳密に言うと、実存主義者の範疇から外れる。
[証明]
清水徹訳『シーシュポスの神話』(新潮文庫)10頁、訳者による註を参照のこと。
実存哲学のことを、カミュは「不条理を見つめていながら、それをつらぬこうとせず、ぎりぎりの段階で飛躍をとげてしまう思考」として批判している。

- 作者: カミュ,清水徹
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1969/07/17
- メディア: 文庫
- 購入: 7人 クリック: 42回
- この商品を含むブログ (80件) を見る
佐藤朔・白井浩司訳『反抗的人間』(新潮社、カミュ全集6)19頁下段
「反抗を分析すると、少なくとも、古代のギリシア人が考えていたように、人間の本性というものが存在するのではないか、という推測に導かれる。これは近代思想の仮定には反する。自己の裡に、保存すべき永遠的なものがないとしたら、なぜ反抗するのだろうか。」
ロベエル・ド・リュペ『アルベエル・カミュ』(新潮文庫)32頁 上記、翻訳部分の真意が、こちらの本の方が明晰に伝わる。 「<自分は実存主義者ではない、>自分にとって本質は実存に先行する、と。<自己のうちに守るべき永久的なものがないとしたら、何故に反抗するのか。>(第二八頁)カミュは次の断定に到る。<現代思想の要請に相反して……人間の本性というものが存在する。>(第二八頁)サルトルへのあてつけをこめて、彼は確信する、<一切の行為に先立って存在するこの価値は、行為のはてに価値は獲得せられる(もし価値が獲得せれるとしたら)と称するところの純粋に歴史的な諸哲学を否定する。>」 ※頁数は『反抗的人間』の原著の頁を指す。

- 作者: リュペ,窪田啓作
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1957
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る
コナー・クルーズ・オブライエン『カミュ』(新潮社、現代の思想家)は、『異邦人』でムルソーに撃ち殺されるアラブ人の無名性に、疑義を投げかけていた。

- 作者: オブライエン,富士川義之
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1971
- メディア: ?
- この商品を含むブログ (1件) を見る
アルジェリア戦争期、サルトルVSカミュ論争の火付け役だったフランシス・ジャンソンは、アルジェリア民族解放戦線FLNを支持し、フランス兵の脱走を幇助する非合法組織「ジャンソン機関」を造り、サルトルも「アルジェリアにおける不服従の権利に関する宣言」、通称「121人宣言」に署名し、「ジャンソン機関」を支持したため、自身のアパルトマンにプラスティック爆弾を投げ込まれたりしたが、カミュが話し合いによる和平の呼びかけに留まったのは、アルジェリアに母親がいたということも関係している。
◆カミュの父親リュシアン・オーギュスト・カミュは、第一次世界大戦のマルヌの戦いで戦死している。その後、カミュは貧困のなかで育った。
伝記的事実が含まれている『最初の人間』(新潮文庫)を参照のこと。
一方、サルトルの父親ジャン=バチスト・サルトルは、開業医の息子だったが、海軍士官として勤務したインドシナで罹った病で死亡した。こちらのほうの家庭状況は『言葉』(人文書院、サルトル全集)および次のブログを参照のこと。
http://monsieurk.exblog.jp/15523098/
◆初期のカミュは、地中海的感性に貫かれている。(『幸福な死』、『表と裏』、『結婚』、『ミノタウロス、またはオランの憩い』)
対比されるべき文学作品としては、アンドレ・ジッドの『地の糧』(新潮文庫)、フリードリヒ・ニーチェの『悦ばしき知識』(ちくま文庫、ニーチェ全集)。
そのなかにおいても、次第に結核による死の翳が作用し始める。
『幸福な死』の主人公メルソーは、メール(海)とソレイユ(太陽)。
その後書かれた『異邦人』の主人公ムルソーは、ムール(死)とソレイユ(太陽)。

- 作者: ジッド,今日出海
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1969/02
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: フリードリッヒニーチェ,Friedrich Nietzsche,信太正三
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 1993/07/01
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 27回
- この商品を含むブログ (25件) を見る
◆カミュは、生粋の演劇人である。
最初は「労働座」、ついで「仲間座」で、次の演目を上演した。
「侮蔑の時代」「商船テナシティー」「蕩児の帰宅」「沈黙の女」「プロメテ」「カラマーゾフの兄弟」「ドン・ジュアン」「どん底」「修道女」「西の国の人気者」
論理的な哲学思考よりも、演劇的ドラマツルギー、肯定と否定の劇的緊張が優先されるケースが多い。
[rakuten:takahara:10254968:detail]
◆ジャーナリストとしてのカミュ
「アルジェ・レピュブリカン」、「ソワール・レピュブリカン」、「パリ・ソワール」で、編集、社説、文芸時評などを行う。
後に、レジスタンス誌「コンバ」の編集主幹となる。
カミュが「自由の証人」として、時事問題を広く論じたのは、この側面があったからである。
2.未完の創作プラン
アルベール・カミュは、『反抗の論理 カミュの手帖―2』(新潮文庫)231頁に、次のように書いている。

- 作者: アルベール・カミュ,高畠正明
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1975
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (2件) を見る
第二の系列。反抗。『ペスト』(それにその補遺)―『反抗的人間』―カリアーエフ。
第三の系列。「審判」―最初の人。
第四の系列。引き裂かれた愛。「火刑」―「愛について」―「誘惑者」。
第五の系列。「改められた創造」、あるいは「体系」―壮大な小説+大いなる瞑想+上演不能の戯曲。」
この書き込みは1947年6月17日から6月25日までの間に書かれた。『ペスト』が刊行された頃である。『反抗的人間』は、刊行前。
つまり、第一の系列に属する仕事は完了し、第二の系列の半ばで、カミュは今後のことも含め、実現したいプランを書いた。
では、どこまでが実現したのか。
『ペスト』の補遺については「『ペスト』拾遺」と、戯曲版『戒厳令』が書かれている。『戒厳令』はペストを擬人化したものだが、あまり面白くない。
カリアーエフは、戯曲『正義の人々』のことだが、「心優しきテロリストたち」という補完する文書も書かれている。
『転落』は、『反抗的人間』刊行後に起きたサルトルとの論争を引きずっている。
主人公のジャン・バチスト・クラマンスは「悔悛した判事」を名乗るが、これは論争の火付け役となったフランシス・ジャンソンの論文へのカミュの反論の仕方が、裁判官のようであり、病理を指摘しているかのようだとサルトルが書いたことに対応しているように思われる。

- 作者: カミュ,大久保敏彦,窪田啓作
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2003/04/24
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 14回
- この商品を含むブログ (24件) を見る
ところで、カミュは、ナチス・ドイツのフランス侵攻の際に、対独抵抗運動(レジスタンス)の機関誌「コンバ(闘争)」の編集主幹だったが、パリ解放後、フランス人の対独協力者に対する粛清(エピュラシオン)問題が浮上する。
ここで行われたのは、カミュと、フランソワ・モーリアックの論争である。
カミュはその際、人間の価値を掲げ、処刑をも容認した。
これに対し、キリスト教作家モーリアックは、慈悲を訴えた。
論争後も、カミュはこの問題について悩み続け、一時的にせよ、処刑を容認する発言をするようになったことを反省するようになる。
そうして、人間の価値を高らかに掲げ、人々の連帯性を説く『ペスト』から、悔悛した転落者の心の紐帯の大切さを説く『転落』へのシフトが進行したのではないか。
第三の系列にある「審判」は、モーリアックやサルトルとの論争を経て、『転落』に変貌した可能性がある。
そして、幼い時に死に別れた父親の姿を再現しようとした『最初の人』。これは未完のまま、死後刊行されることになる。
こうしてみると、カミュは第三の系列の半ばで、正に不条理とも言える不慮の交通事故で亡くなったといえる。
第一の系列では、高い山に大きな岩を押し上げようとするが、まっさかさまに転がり落ちるシーシュポスの不条理な運命が扱われ、過酷な状況のなかでの幸福が追求された。
第二の系列では、人間に火を教えたプロメテウスが、反抗的人間として称揚される。
第三の系列では、均衡に外れた、行き過ぎた行いを裁くネメシスが注目される。
第四の系列では、愛が主題となり、ディアネイラが注目されることになるはずだったが、カミュが未着手の領域なので、彼のなかでどう位置づけられるのかが判らない。
第五の系列では、改められた創造とあるだけに、この既成の世界に代わる世界を創造せんとする芸術の役割が強調されると想像されるが、やはり、全容はまったくわからない。
兎も角、カミュが初期の段階で、その後書こうとする内容の方向性を決めていたことは間違いない。
3.不条理の系列
主要作品解題
(1)不条理の系列
『異邦人』
「今日、ママンが死んだ。」から始まる衝撃作。
母の死の翌日、ムルソーは女と関係を結び、喜劇映画を見て笑い転げる。母の死ですらも、日常に埋没した意識から、彼を覚醒させることはない。ムルソーは友人の女出入りに関係して、アラブ人を殺害し、動機は「太陽のせい」と答える。
変貌を遂げるのは、死刑を宣告された後の最終シーンである。告悔に訪れた神父に向かって、「女の髪の毛一本の価値もない」という。ムルソーのなかで何かが弾け、彼は自身が幸福であると確信する。

- 作者: カミュ,窪田啓作
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1963/07/02
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 21人 クリック: 167回
- この商品を含むブログ (411件) を見る
『異邦人』を読むのに、コリン・ウィルソンの『アウトサイダー』が、ひとつの視点を与えてくれるだろう。死を意識したとき、ムルソーは覚醒し、意識の拡大(後のコリン・ウィルソンは「至高体験」と呼ぶようになる)を経験するのだ。

- 作者: コリン・ウィルソン,中村保男
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2012/12/20
- メディア: 文庫
- 購入: 46人 クリック: 1,852回
- この商品を含むブログ (22件) を見る

- 作者: コリン・ウィルソン,中村保男
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2012/12/20
- メディア: 文庫
- 購入: 38人 クリック: 171回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
『シーシュポスの神話』
「不条理の思想」を解き明かす、詩的イメージに満ちた哲学的エッセイ。
人生の根本問題は、人生は生きるに値するか否か、つまり自殺の是非だとして、カミュは人生の無意味さ(不条理)について検討を加えてゆく。
このエッセイは、死を宣告された芸術家が、芸術的な感性によって、次第に生の高揚感に取り憑かれ、最期は至高体験に到達するという物語のようにも思える。
山上に岩を押し上げるというシーシュポスの無限の労苦が、死と向き合った生のかたちを見つめ直すことで、輝きを帯びた幸福感に包まれる。
『カリギュラ/誤解』
ともに不条理を主題とした戯曲である。
「カリギュラ」を<動>とすると、「誤解」は<静>である。
「カリギュラ」は、最愛の妹ドリュジラを亡くしたローマ皇帝カリギュラは、人はすべて死なねばならぬという世界の根源的不条理に叛逆するために、狂気に満ちた市民の無限殺戮を敢行し、最後の標的である神を駆り出そうとする。
「誤解」は、自分の名前を名乗らなかったがために、母親に殺害される息子の物語。マルタとその母は、田舎のホテルを経営していたが、暗い国から太陽の降り注ぐ国に移ろうと、宿泊客を殺害し、金品を奪っていた。マルタの兄ジャンは、大昔に家出をしたが、街で成功し帰ってくる。しかし、母親たちを驚ろかせようと、身分を隠して宿泊し、殺害される。

アルベール・カミュ (1) カリギュラ (ハヤカワ演劇文庫 18)
- 作者: アルベール・カミュ,Albert Camus,内田 樹(解説),岩切正一郎
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2008/09/25
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 42回
- この商品を含むブログ (25件) を見る

- 作者: アルベール・カミュ,渡辺守章,鬼頭哲人
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1971/01
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (11件) を見る
4.反抗の系列
主要作品解題
(2)反抗の系列
『ペスト』
伝染病という不条理に見舞われたオラン市を舞台に描くパニックもの。
執筆段階ではタイトルは、「囚人たち」だった。
ナチス・ドイツの侵攻を受けたパリにおいて、カミュはレジスタンスの運動に深く関与したが、このときの経験によって、カミュの文学的主題は、不条理に対する人々の集団的反抗(連帯性の強調と、反抗への力点の移動)となる。
カミュは、フランス象徴主義の継承者であったから、このレジスタンスの記憶を、ペストによる監禁状態に置き換えることによって、何人の人生にも関わりの深い、人生の不条理への抵抗という主題に変容させた。
本書の主人公は、医師リウーであり、その哲学的分身がタルーという不条理の観察者である。
その他、新聞記者のランベール、神父パヌルーなど、それぞれの立場で、ペストという問題と格闘する。
神父パヌルーは、カミュが理解するところのキリスト教的実存主義と二重写しになっており、人生の不条理さえも神の用意したものである以上、人間の理解しえないものを受け入れないといけないといった主旨の事を言うが、リウーは罪なき幼児の死をどう考えるのかという問いを突き付ける。
(罪なき幼児の死を突きつけるやり方は、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」におけるイワンを想起させる。)

- 作者: カミュ,宮崎嶺雄
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1969/10/30
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 4人 クリック: 104回
- この商品を含むブログ (83件) を見る
『反抗的人間』
かつて『シーシュポスの神話』で、自殺を否定したカミュは、本書において、殺人を肯定する理論をニヒリズムとして否定する。
本書に収められた「ロートレアモンと平俗」「シュルレアリスムと革命」の章は、アンドレ・ブルトンとの論争を引き起こした。
しかし、本書で主に批判されているのは、マルクス主義である。(本書の刊行年は1951年。タイミングからして、メルロ=ポンティの『ヒューマニズムとテロル』1947年が仮想的と思われる。)
『異邦人』の最終シーンでは、個人的美徳としてのキリスト教が批判対象となっていた。『反抗的人間』では、集団的美徳としてのマルクス主義が批判対象となっている。
カミュの論法は、理想的な未来社会の実現のために、今日の何万、何十万の人々が革命の名のもとに殺されるのは、納得がいかないということであり、そのような殺人を肯定する論理が出てくるのは、歴史を神格化する歴史主義なのだという。
こうして、カミュは均衡を失った(正午の思想に反する)過激な革命思想を排し、その代わりに人々の連帯性に基づく反抗を説くのである。
この『反抗的人間』に対して、サルトルによる『ル・タン・モデルヌ』誌は、フランシス・ジャンソンによる批判論文を掲載し、この批判に対して、カミュは『ル・タン・モデルヌ』編集長のサルトルへの抗議文を送り、それに対してサルトルとジャンソンによる反論が行われた。これがサルトルVSカミュ論争である。
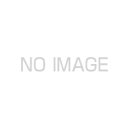
革命か反抗か カミュ=サルトル論争 新潮文庫 / 佐藤朔 【文庫】
- ジャンル: 本・雑誌・コミック > 小説・エッセイ > 外国の小説
- ショップ: HMV&BOOKS online 1号店
- 価格: 497円
『戒厳令』
『ペスト』の戯曲版で、ペストが擬人化されているが、教訓色が強まり、演劇としては失敗作であろう。
『正義の人びと』
帝政ロシア末期のテロリスト群像を題材に、彼らの革命観における倫理にスポットをあてた戯曲。
主人公のカリャーエフ(ヤネク)は、セルゲイ大公の馬車に爆弾を投げつけようとするが、大公妃と2人の子どもが同乗しており、子どもと眼のあったカリャーエフは、爆弾を投げることができなくなり、拠点に戻ったカリャーエフは、仲間たちから総括を受け、再びカリャーエフが爆弾を投げることになるのだが……。
カミュは、テロリストたちにたびたび、愛について議論させている。憎しみが支配するようになれば、革命は成功するのかも知れない。しかし、そのとき革命は民衆の敵になるのかも知れない。ロシアへの愛は、今も存在するのか。
最終的に、カリャーエフが辿り着くのは、ロシアへの愛ゆえに、一人をテロルで殺したならば、自らも自死しなければならないという、究極的な倫理の限界点である。
カミュはかつて存在したテロリスト群像を描いたのは、今日、何万、何十万の人々の死を正当化するような論理が知識人の間でまかり通っている事に対する対比の意味においてではないかと思われる。

テロリスト群像 上/サヴィンコフ/川崎浹【3000円以上送料無料】
- ジャンル: 本・雑誌・コミック > 文庫・新書 > 文庫 > その他
- ショップ: bookfan 1号店 楽天市場店
- 価格: 1,080円
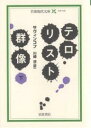
テロリスト群像 下/サヴィンコフ/川崎浹【1000円以上送料無料】
- ジャンル: 本・雑誌・コミック > 文庫・新書 > 文庫 > その他
- ショップ: bookfan 2号店 楽天市場店
- 価格: 1,188円
付録 フランス政治思想史の重要著作
◆1946年 「唯物論と革命」ジャン=ポール・サルトル
既成マルクス主義は、機械論的唯物論に陥っているという実存主義からの批判。
◆1947年 『ヒューマニズムとテロル』モーリス・メルロー=ポンティ
モスクワ裁判を分析、スターリン主義を擁護する内容。
[rakuten:takahara:10103990:detail]
◆1948年 RDR(革命的民主同盟)を結成。ジョルジュ・アルトマン、ダヴィッド・ルーセ、サルトルらが参加。
インターナショナルフランス支部(後の社会党)と、フランス共産党の両者と一線を画した中道左派グループ。
◆1948年12月 カミュ、アンドレ・ブルトン、エマニュエル・ムーニエらが、世界市民宣言を行ったゲーリー・ディヴィスへの支持を表明。
◆1949年 サルトル、RDRを脱退。
ダヴィッド・ルーセが米国の労働組合から資金援助を得るようになったのがきっかけ。
◆1950年1月 「ソ連と収容所」(のちに『シーニュ2』に収録)メルロ=ポンテイ
ソ連に強制収容所が存在することを告発。
◆1950年 「われらの生の日々」(『ル・タン・モデルヌ』1月号)メルロ=ポンティ&サルトル
ソ連に強制収容所が存在したという事実に対し、「強制収容所の恐怖のごとき絶対の経験でさえひとつの政策の決め手にはならない」と主張。「いかなる場合でも共産主義の敵と妥協はできない」と言明。
◆1951年 『反抗的人間』アルベール・カミュ
マルクス主義を、歴史を神格化し、殺人を肯定する理論として批判。
◆1952年〜54年 「共産主義者と平和」ジャン=ポール・サルトル
フランス共産党書記長代理のデュクロらが、暴動を企てた容疑で逮捕。共産党と労働総同盟(CGT)がゼネストを組織するも失敗。サルトルは、デュクロ事件を契機に左傾化、状況分析から、ソ連側を平和勢力と同一視するようになる。
◆1953年 『ル・タン・モデルヌ』4月号に、「共産主義者と平和」を巡って、クロード・ルフォール(メルロ=ポンティの門下生)とサルトルの論争が掲載される。メルロ=ポンティとサルトルの不協和音。
◆1953年7月 サルトルとメルロ=ポンティの決裂が起こる。
ふたりの往復書簡(当時、非公表)は、現在、『サルトル/メルロ=ポンティ往復書簡』で読むことができる。
◆1955年 『弁証法の冒険』モーリス・メルロー=ポンティ
サルトルも、既成マルクス主義も、ともに弁証法を失ったウルトラ・ボルシェヴィズムであるとして非難。非共産主義的左翼を提唱。
[rakuten:guruguru2:11135881:detail]
◆1960年 『方法の問題―弁証法的理性批判序説』ジャン=ポール・サルトル
マルクス主義と実存主義を融合。実存主義をマルクス主義に寄生するイデオロギーとして位置づけ。
◆1960年 『弁証法的理性批判』ジャン=ポール・サルトル
歴史は、集団の実践作用(プラクシス)が造りだすとし、「構造」もまた実践的惰性態に過ぎす、プラクシスによって変えることが可能とする。
◆1962年 『野生の思考』クロード・レヴィ=ストロース
サルトル的コギトは、西欧のローカルな産物とし、自民族中心主義を批判。構造は変えられない。むしろ、構造が人間を規定すると主張。構造主義へのシフトが起こる。
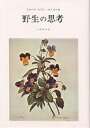
◆1974年 『反逆は正しい』ジャン=ポール・サルトル、フィリップ・ガヴィ、ピエール・ヴィクトール
次第に盲目になっていくサルトルは、書くことから、話すことに哲学表現を変えていく。そこに話し相手兼秘書として登場したのは毛沢東派の青年ピエール・ヴィクトールである。彼は『弁証法的理性批判』の領域を超えて、サルトルを既成政党よりも左に連れ出そうとし、大衆啓蒙的な小説を書かせようとするのだが、サルトルは『家の馬鹿息子』の完成に執着し続ける。
◆ジャン=ポール・サルトルについて私が知っている二、三の事実 (1)
レイモン・アロン(フランスの社会学者、哲学者。政治的には保守的陣営)は、モンパルナスのベック・ド・ギャーズという店で、杏のカクテルを頼み、『君が現象学者なら、このカクテルについて語れるんだよ。そしてそれは哲学なんだ』とサルトルに語った。それが、サルトルと現象学の出会いだ。
ドナルド・D・パルマーの漫画『サルトル』(ちくま学芸文庫)は、杏のカクテルを生ビールに変えてしまった。訳者の澤田直は、サルトルの新訳を出している人物だが、カクテルがビールにすり替えられている事に気付かなかったのだろうか。

- 作者: ドナルド・D.パルマー,Donald D. Palmer,沢田直
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2003/10
- メディア: 文庫
- 購入: 3人 クリック: 25回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
サルトルが、フッサールの現象学で特にインスパイアされたのは、意識の志向性という事であった。意識は、常になにものかについての意識であるという志向性は、サルトルの積極的に行動を促す哲学の基礎となった。事物に向かう時だけ、意識は存在する。これを集団的レベルで考えるならば、国家に対峙している時だけ、ヴィヴィッドに意識は実存するということになる。何もせず、怠惰に水いらずの環境下で眠り込んでしまえば、意識は死んだも同然である。
ちなみに、モーリス・メルロ=ポンティの場合、生活世界を巡る後期のフッサールの影響を受けていて、『行動の構造』や『知覚の現象学』は、心身二元論の克服を目指しており、精神と肉体のキアスムを追及したり、晩年になると、独自の<肉>の思想に向かっていく。ハイデッガーの「世界−内−存在 in-der-Welt-sein」を、サルトルがL'etre-dans-le-mondeと直訳したのに対し、メルロ=ポンティが「世界−内属−存在 L'etre-au-monde」と存在の内属性を強調した訳し方をしたのも、心身二元論から来る独我論を克服しようとしたためである。『ル・タン・モデルヌ』誌の実存主義グループということで、サルトルと同イメージで捉えられることの多いメルロ=ポンティだが、彼の立場からするとサルトルの『存在と無』は、心身二元論に陥っており、克服せねばならない対象であったと考えられる。

- 作者: モーリス・メルロ=ポンティ,竹内芳郎,小木貞孝
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 1967/12/01
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 29回
- この商品を含むブログ (33件) を見る
捕虜収容所で、サルトルは本の差し入れを要求する。マルティン・ハイデッガーの『存在と時間』である。 1943年に刊行されたサルトルの『存在と無』は、フッサールの現象学とハイデッガーの『存在と時間』の影響を受けている。

- 作者: ハイデガー,熊野純彦
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2013/04/17
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (14件) を見る

- 作者: ハイデガー,熊野純彦
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2013/06/15
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (5件) を見る

- 作者: ジャン=ポールサルトル,Jean‐Paul Sartre,松浪信三郎
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2007/11/01
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 56回
- この商品を含むブログ (55件) を見る

- 作者: ジャン=ポールサルトル,Jean‐Paul Sartre,松浪信三郎
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2007/12/10
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 11回
- この商品を含むブログ (21件) を見る

- 作者: ジャン=ポールサルトル,Jean‐Paul Sartre,松浪信三郎
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2008/01/09
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 10回
- この商品を含むブログ (20件) を見る
後にサルトルは『実存主義はヒューマニズムである』で、有神論的実存主義と、無神論的実存主義に分け、ハイデッガーを後者に分類するが、これは二重の意味で間違いであった。第一に、ハイデッガーは存在教、存在主義者であったが、実存主義者ではなかった。実存を分析したのは、存在とは何かという答えに近づくための手段に過ぎなかった。第二に、無神論というのも間違いだった。確かにハイデッガーの哲学に神は登場しないが、存在が哲学用語で語られた神、存在者を存在者たらしめるものであった。いわば、神は不在だが、神の座る王座は常に用意されており、いつでも帰還を待っているという状態だったのだ。

- 作者: ジャン=ポール・サルトル,伊吹武彦
- 出版社/メーカー: 人文書院
- 発売日: 1955/07/30
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
『存在と時間』と『存在と無』は、死生観においても対称的である。『存在と時間』において、死は本来的自己や良心を呼び覚ますための高次の法廷のような位置づけになっている。これに対し、『存在と無』において、人間の生き死には、偶然性にゆだねられている。人は意味もなく、世界の中に投げ込まれて、まず、ただ単に存在する。いわば、ゼロ地点としての人間存在としてサルトルによっては捉えられているのだが、サルトルはそこから逆手にとって、人間をゼロから出発する無限の可能性を持ったものとして捉えなおす。ただ、これから来る世界に向けて、前向きに自己を投企することに意義があるという訳である。
アンガージュマン、自己を拘束すると同時に、政治参加を含意する意味の言葉だが、サルトルはそこに価値を与える。積極的に、政治などに関与すること。サルトルの哲学は、アクティヴに状況に介入することに意味づけをする哲学である。
これが『実存主義はヒューマニズムである』の時期になると、人間中心主義という方向性が打ち出され、価値の萌芽がみられるようになる。
最近、フランスではサルトルの再評価が見られるようになり、そのきっかけはベルナール・アンリ・レヴィの『サルトルの世紀』のせいなのだが、これは「実存主義はアンチ・ヒューマニズムである」という仮定に立って、ポストモダンの思潮を先駆するものとして読み解こうとするものである。
ベルナール・アンリ・レヴィは、新哲学派(ヌーヴォー・フィロゾフ、ソルジェーニーツィンの『収容所群島』以降、マルクス主義は収容所に帰結すると改心したイデオローグたち)の論者としてデビューしたが、その後、人権問題などに取り組むようになった。ベルナール・アンリ・レヴィの問題系は、人間の名の下に行われる野蛮な悪政である。

- 作者: ベルナール=アンリレヴィ,Bernard‐Henri L´evy,石崎晴己,三宅京子,沢田直,黒川学
- 出版社/メーカー: 藤原書店
- 発売日: 2005/06
- メディア: 単行本
- クリック: 6回
- この商品を含むブログ (15件) を見る

- 作者: 清眞人
- 出版社/メーカー: 藤原書店
- 発売日: 2012/12/21
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
◆ジャン=ポール・サルトルについて私が知っている二、三の事実 (2)
サルトルの『実存主義はヒューマニズムである』(1945年10月、パリのクラブ・マントランで行われた講演「実存主義はヒューマニズムであるか」の記録)は、通俗的にせよ、実存主義とは何かを広く膾炙させたことは間違いない。
実存主義のブームが去った後、構造主義、記号論、ポスト構造主義、新哲学派……と次々と思想のモードが変容した。
今さら、実存主義とは何だったのか、検証する意義はあるのかと思われるかもしれない。しかし、人が真摯に生きようとしたならば、実存的にならざるを得ない。時代と共に世界観が(ポスト構造主義やポスト記号論に)変わったとしても、真にリアルに生きようとしたならば、実存から始めるしかない。「主義」としてはどうなのかはわからない。また、「実存論的」思考が、今後も有効なのかもわからない。しかし、「実存論的」ではなく、「実存的」に、誰でもない、他ならぬこの私自身が自覚的に生きようとするとき、必ず「実存的」にならざるを得ない。武器として、あるいは手段としての「実存主義」はともかく、「実存哲学」が今後も有効なのは間違いない。
『実存主義はヒューマニズムである』は、日本では『実存主義とは何か』として刊行されている。
実存主義は、本質主義の反対語であり、実存は本質に先立つということである。
人間がペーパーナイフを造る際に、ペーパーナイフは紙を切るものといった属性(本質)を考え、それに基づき造形を行う。つまり、ペーパーナイフにおいては、本質がまず先にあって、それから実際に存在させられる。
しかし、人間はどうか。サルトルは、人間の場合、初めに人間の概念規定がないとして、人間はなりたい自分になるのだとする。人間は、まず実存し、それから自分自身で、自分の考える未来像に形を与えるのである。
サルトルは、有神論的実存主義と無神論的実存主義を分け、前者にキルケゴール、ヤスパース、マルセルらを入れ、後者にニーチェ、ハイデッガー、そしてサルトル自身を入れる。
サルトルに言わせると、無神論的実存主義の方が、首尾一貫しているという。神がいないので、人間はかくあるべしという本質の規定がないというわけである。
なお、有神論的実存主義であるカール・ヤスパースもまた、「人間であることは、人間になることである。」と言っている。ヤスパースにおいては、神が存在することと、実存することは矛盾しない。よりリアルに実存するほど、神が存在することが実感されてくるというわけだ。
ここで、本質主義と敵対する実存主義の意味を、別の角度から考えてみたい。それは、ヴィクトール・フランクルの『精神医学的人間像』における本質主義批判である。
フランクルは、ナチス・ドイツのユダヤ人強制収容所の生き残りであり、『夜と霧』の著者である。彼は、強制収容所のガスかまどで殺される寸前まで行った経験を元に、ロゴセラピーという独自の精神医学を築いた。
『精神医学的人間像』は、ユダヤ人の大量虐殺を行ったのは、ドイツ兵であるが、その背景には、人間は「血と土(遺伝と環境)」で決まるという歪んだホムンクリスムス(人造人間合成術)があったとする。ホムンクリスは、ゲーテの『ファウスト』に出てくるファウストがつくった人造人間である。一面的な人間理解に基づいて造られているので、ホムンクルスの夢は瓦解してしまう。フランクルは、ホムンクリスムスは本質主義だとする。人間を外面的に観て、「人間は〇〇に過ぎない」というのが、本質主義である。フロイトのように、人間を性的欲望(lリビドー)を抱えた衝動機械とするのも、本質主義である。本質主義的な人間理解は、一面的な見方であり、全体を捉えたものではない。人間は「〇〇にすぎない」ではなく、「〇〇からはじまる」存在、未来へと投企する存在なのである。こうして、フランクルは本質主義(に基づく差別〜民族虐殺)を斥け、人間の内なるロゴスを開示する方向に向かう。

- 作者: ヴィクトル・E.フランクル,Victor Emil Frankl,宮本忠雄,小田晋
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 2002/09/21
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: V.E.フランクル,霜山徳爾
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 1985/01/23
- メディア: 単行本
- 購入: 11人 クリック: 101回
- この商品を含むブログ (120件) を見る

- 作者: ホルクハイマー,アドルノ,Max Horkheimer,Theodor W. Adorno,徳永恂
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2007/01/16
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 89回
- この商品を含むブログ (79件) を見る
◆ジャン=ポール・サルトルについて私が知っている二、三の事実 (3)
サルトル『嘔吐』は、『存在と無』の小説版である。アントワーヌ・ロカンタンが、マロニエの木の根に吐き気を覚えるのは、そこに本質を削ぎ落とされた剥き出しの即自存在を見たからである。ここで注視しておきたいのは、ロカンタンが見出した吐き気の症状からの脱却の手がかりが、サキソフォンの調べ、つまり音楽芸術だったということである。 サルトルの存在論において、美は意識の無化作用と結びついている。存在そのもの(裸形の存在)が、時として「水いらず」への嫌悪、またある時には吐き気を催させるのに対し、芸術は存在の世界に無を胚胎させる。

- 作者: J‐P・サルトル,白井浩司
- 出版社/メーカー: 人文書院
- 発売日: 1994/11/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 74回
- この商品を含むブログ (88件) を見る
『存在と無』から『弁証法的理性批判』に至る途中で、サルトルの新たな転回点となったのは、ジャン=ジュネ論『聖ジュネ』である。

- 作者: サルトル,白井浩司,平井啓之
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1971
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る

- 作者: サルトル,白井浩司,平井啓之
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1971
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る

- 作者: ジャンジュネ,朝吹三吉
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1968/10/02
- メディア: 文庫
- 購入: 6人 クリック: 186回
- この商品を含むブログ (42件) を見る

- 作者: ジャン・ジュネ,鵜飼哲,海老坂武
- 出版社/メーカー: 人文書院
- 発売日: 1994/03/15
- メディア: 単行本
- クリック: 49回
- この商品を含むブログ (17件) を見る

- 作者: ジャンジュネ,Jean Genet,鵜飼哲,梅木達郎
- 出版社/メーカー: インスクリプト
- 発売日: 2010/06/01
- メディア: 単行本
- クリック: 26回
- この商品を含むブログ (16件) を見る
ジュネは売春婦の子どもとして生まれ、田舎の家庭に養子として預けられる。ジュネは成績は申し分がなかったが、すべてが借り物の世界において、盗みによって自分のものにしようとする。(その後刊行されたサルトルの自伝『言葉』と重ねあわせると、サルトルは父なし子として親戚の家に預けられた自分が経験した疎外感から、幼年期のジュネの精神状況を類推しているのではないか、という感慨を起こさせる。)
決定的な事が起こったのは、ジュネが盗みの瞬間を見られ、泥棒というレッテルを貼られたことである。泥棒というレッテルをはねつけることができない幼年期のジュネは、むしろ積極的に泥棒たらんとし、泥棒であることを突き詰めることによって、状況の突破口にしようとする。
乞食、窃盗、男娼、麻薬密売……あらゆる悪事を極めようとしたジュネは、現実よりも虚構の、殺人を鼓舞するような文学作品を書くことが、より高度の悪であるとして、泥棒から審美家へと変身を遂げる。現実の犯罪は醜い。しかしながら、ジュネの創造する文学空間においては、悪は装麗化され、聖なるものに変わる。
サルトルは、ジュネの実存の内側から、自由へと向かうジュネの精神の軌跡を辿り、善と悪、美と醜、聖と俗がめまぐるしく転回する世界を暴き出した。
『聖ジュネ』によって、内面の秘密を暴かれたジュネは、しばらく書けなくなったという。
しかしながら、怪物作家の力量は、これで終わることがなかった。ジュネは小説から劇作に進み、劇中において善と悪、美と醜、聖と俗がめまぐるしく転回する世界を描いたかと思うと、サルトル的弁証法の軌道を超えて、ブラックパンサーと、さらにはPLOと組んで、政治へのコミットを始め、やがて『恋する虜』を書くことになる。
ジュネの存在は、その後も現代思想に激震を与え続け、ジャック・デリダに『弔鐘(グラ)』を書かせることになる。
サルトルの作家論としては、初期の『ボードレール』、後期の『家の馬鹿息子』などがあるが、中期の『聖ジュネ』が一番刺激的である。
『聖ジュネ』を読むとき、私が思い起こすのは、親鸞の「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」という言葉である。サルトルは、悪人の内面に没入して、悪人が聖人に生成変化を遂げるまでを追っていく。何という極限的なヒューマニズムだろう。普通、このような試みは、ヒューマニズムとは言わない。サルトルは、一般社会から排除された人間さえも見離すことなく、内側から信じ切ってみせたのである。
◆ジャン=ポール・サルトルについて私が知っている二、三の事実 (4)
今回は、以前に書いた「アルベール・カミュに関するノート 付録 フランス政治思想史の重要著作」を横目で見ながら、お読みください。
存在論である『存在と無』の後、サルトルは当為論である『倫理学』を書こうとして、挫折し、ノートだけが残されます。『聖ジュネ』という転回点を経て、サルトルは『弁証法的理性批判』に向かいます。
『方法の問題』は、『弁証法的理性批判』の序文で、サルトルの狙いが判ります。
まず、サルトルはマルクス主義を、マルクス主義を生み出した状況が解決できていないため、現代の乗り越え不可能な哲学であり続けているとします。
その上で、自身の実存主義を、マルクス主義に寄生するイデオロギーとして位置づけます。マルクス主義の官僚主義化・教条主義化といった動脈硬化に対して、実存主義は主体主義的ヒューマニズムの立場から改善するというのです。
『弁証法的理性批判』の最重要概念は「実践惰性態」です。これは、レヴィ=ストロースの言うところの「構造」に対応しています。
レヴィ=ストロースは、『ル・タン・モデルヌ』に寄稿したこともあり、ボーヴォワールの『第二の性』も、レヴィ=ストロースの初期の大著『親族の基本構造』の草稿である『親族の構造』を取り寄せて、その研究成果を取り入れて書いたという研究があります。(http://www.kinjo-u.ac.jp/nakata/pdf/Beauvoir2.pdf)
思想史の観点からすると、サルトルの『弁証法的理性批判』が先にあり、レヴィ=ストロースの『野生の思考』がそれを撃破したということになっていますが、サルトルは構造主義が思想のモードとして浮上する前に、それを批判し、潰しておこうとしたと、私は考えます。
「構造」は、諸個人の実践作用(プラクシス)を規定しますが、「実践惰性態」と言い換えることで、人間が造った制度である以上、諸個人の実践作用(プラクシス)で変えられないはずはない、ということになります。
サルトルは構造主義者が「歴史」をつくろうとしないことを攻撃します。人間が歴史をつくる、とサルトルは言い、諸個人の実践作用(プラクシス)を最重要視します。
サルトルの先制攻撃に対し、レヴィ=ストロースは『野生の思考』の結論部分において、サルトルにおけるデカルト的コギトは、普遍性のあるものではなく、西欧社会のローカルなものに過ぎず、人間の思考は、実は共同体の「構造」に規定されていると主張します。
これに対し、サルトルは、レヴィ=ストロースは分析的理性は判っても、弁証法的理性の事は判っていないのだとします。
レヴィ=ストロースの『野生の思考』の後、構造主義的な思潮(ここで言う構造主義は、ジャーナリスティックな用語と考えるべきです。構造主義者フーコーに構造はなく、アルチュセールは構造主義者という言い方を拒否し、ラカンの構造概念は動態論的になっています。彼らの共通点は、実体論ではなく、関係論的アプローチをする事くらいです。)が噴出します。
『言葉と物』のミシェル・フーコーは、ニーチェの影響を示しつつ、人文諸科学における「人間の死」と宣言し、人間の思考を規定するエピステーメーが変わりつつあることを示しました。

- 作者: ミシェル・フーコー,Michel Foucault,渡辺一民,佐々木明
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1974/06/07
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 55回
- この商品を含むブログ (175件) を見る

- 作者: ルイアルチュセール,Louis Althusser,河野健二,西川長夫,田村俶
- 出版社/メーカー: 平凡社
- 発売日: 1994/06/01
- メディア: 新書
- 購入: 2人 クリック: 25回
- この商品を含むブログ (19件) を見る

- 作者: ルイアルチュセール,ピエールマシュレー,ジャックランシエール,Louis Althusser,Pierre Macherey,Jaques Ranci`ere,今村仁司
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 1996/10
- メディア: 文庫
- クリック: 9回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
この後、リュシアン・セバーグが、『構造主義とマルクス主義』を書き、社会変革に消極的な構造主義を造り変えることによって、倫理性と科学性の両立を図ろうと図りますが、勿論、この作業は理論的困難を極め、彼は構造主義とマルクス主義の間で引き裂かれ、自殺します。
ポスト構造主義(『監獄の誕生』以降のフーコー、『アンチ・オイディプス』『ミル・プラトー』のドゥルーズ=ガタリ、『エコノミー・リビディナル』のフランソワ・リオタールら。ネグリの著作も、この延長線上にあると考えられます。)の試みは、倫理性(社会にアンガジェする!)と科学性(社会科学的にも正しい)の両立の企てと観ることができますが、人間の思考と、人間の行動と、現実変革の効果の関係に、不明瞭な部分が残ります。
こうした状況に対し、北見秀司の『サルトルとマルクス』は、ネオリベラリズムが支配する現代を批判する視座の獲得のために、再度、サルトルの後期を見直し、ポスト構造主義が解決できていない問題を、実は構造主義を批判的に乗り越えようとした『弁証法的理性批判』がすでに解決しているのではないか、と未来の思想としてサルトルを思考するのです。北見の論は、常識的な思想史の見方をひっくり返すもので、それが成功しているかは『サルトルとマルクス』を各自読んでいただくしかありません。

- 作者: 北見秀司
- 出版社/メーカー: 春風社
- 発売日: 2010/03
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 北見秀司
- 出版社/メーカー: 春風社
- 発売日: 2011/04
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
![最初の人間 (新潮文庫) [ アルベール・カミュ ] 最初の人間 (新潮文庫) [ アルベール・カミュ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4117/9784102114117.jpg?_ex=128x128)
![幸福な死改版 (新潮文庫) [ アルベール・カミュ ] 幸福な死改版 (新潮文庫) [ アルベール・カミュ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4087/9784102114087.jpg?_ex=128x128)
![カラマーゾフの兄弟(2) (光文社古典新訳文庫) [ フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフス ] カラマーゾフの兄弟(2) (光文社古典新訳文庫) [ フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフス ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3347/33475117.jpg?_ex=128x128)


